黄昏の契約Ⅳ
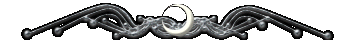
忘却された存在は死者。
忘却されたから死者なのか。
死者だから忘却されたのか。
彼女は笑って答えた――「人によっては忘却こそが救い」と。
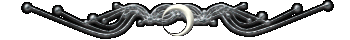
一
は、あぁ……
陶然とした男の溜め息を耳にして、女は煽情的な赤い唇に笑みを浮かべた。
濡れた唇から零れるのは甘い吐息。
「これは、夢だろうか……」
男の呟きに女は縋るような表情で見つめ返した。
「夢ならば忘れてしまわれますか?」
「……いいや、夢であるはずがない。貴女のような美しい人を忘れることはしない」
その答えに女は静かに微笑む。
「わたくしも忘れはいたしません」
その微笑みに誘われるように、男は女の唇を奪い、貪る。
飢えを満たすかのような、くちづけ。
飢えていたのはどちらであったのか。
満たされることを望んだのはどちらであったか。
やがて。
男は恍惚の表情を浮かべたまま、時を止める。
虚ろな双眸に女を映して。
やがて。
女は悲哀の表情を浮かべたまま、唇を拭う。
愁いげな双眸に男を映して。
「わたくしは、忘れはいたしません」
女は静かに瞳を伏せ、自らの左胸に手を当てた。
規則正しい鼓動。
生命の営み。
巡る力。
それを確かめ、女は安堵の笑みを浮かべた。
「この想いを、忘れはいたしません」
誓いの言葉を聞く者は誰もいなかった。
二
「やはり、此処に来て正解だったな」
露台に立って、彼は久方ぶりの開放感を味わっていた。
緑豊かな自然と近くにある湖がもたらす涼やかな空気は彼の今までの心労を確実に癒していた。
最近、聖都にいてはろくなことがないと感じていたこともあり、気分転換のつもりで彼は聖都から離れた避暑地に来ていた。
「どうかね、其処から見える景色は?」
不意に声をかけられ、彼が振り向くと、部屋の中に、この別邸の主である男が立っていた。
父の友人で、近く義理の父ともなる男はにこやかな笑顔で近付いて来る。
それを見て、彼は努めて穏やかな笑みを浮かべた。
今まで何度か誘われていたのだが、彼は何かと理由を付けてすべて断っていた。
その彼がようやく誘いを受けたことに男は満足しているらしかった。
権力はあっても、名誉はない男は自分の娘を初代聖王の時代から続く聖騎士の家柄である彼と婚姻させようとしていた。
基本的にそういうことに興味ない彼は全く気にも留めておらず、多少の煩わしさを感じるだけであった。
「素晴らしいですね」
表情こそは取り繕ったが、言葉は本当だった。
景色もだが、何より、あの思い出すも憎たらしい人外の存在を感じさせない空気が喜ばしい。
精霊と呼ばれる異形の者はいるのが、それは取るに足りないことである。
当り障りない話をして、男が婚儀の予定を決めようとするのを適当に答えていると、彼は周囲の精霊たちが騒ぎ始めたのに気付いた。
何やら、彼を何処かに連れて行きたそうな雰囲気だ。
しかし、彼が無視していると、精霊たちは悪戯を始める。
内心、舌打ちして彼は夕食前の散策に出かけると言って、外に出た。
精霊たち自身は大した力を持っておらず、害はない。
だが、その悪戯は侮り難い。しかも、絶妙な連携で行われる。
彼らの望みは大抵些細なことだと分かっているので、彼は時間が許す限りは付き合っていた。
時には鳥の雛が孵ったとか花が咲いたとか余りにも些細過ぎて、逆に腹立たしいこともあるのが、大変なことよりも随分マシであろう。
さて、今回は何だろうと思案しながら、精霊たちの誘うままに彼は歩き出した。
彼が自分の考えが甘かったことを思い知ったのは、精霊たちに囲まれながら、大木の幹に体を預けている男と視線が合った瞬間だった。
「……そう、か……。精霊、たちが何処へ行くのか、不思議に……思っていたのですが」
息も絶え絶えに呟いた男は全身を朱に染めていた。
普通の人間なら、とうの昔に息絶えていたことだろう。
しかし、あいにく男は人間ではなかった。
そうであることが、彼には分かってしまった。
「聖眼の主を、呼びに……行った、のですね」
そして、男は死相が浮かんだ顔で微笑んだ。
『聖眼』とは人外の存在を見る力だ。
そして、彼には不幸にも、その能力があった。
聖眼のせいで、一体どれほどの精神的苦痛を味わったことか。
自然、彼は仏頂面になるのを感じた。
出来ることなら今すぐにでも踵を返し、何も見なかったことにしたかった。
それが出来なかったのは男が今にも事切れそうだというのに彼を呼んだからだった。
「聖眼の主よ……」
「……何だ?」
答えたことに、彼が話を聞くつもりがあると知って、男は儚く笑んだ。
そして、独白するかのように小さく呟く。
「良かった……。私は――これで、死ねる……」
男は緩慢な動きで右腕を上げ、ゆっくりと自らの右眼に手を当てた。
そして。
ぐちゅ……
男は指を捻じ込み、自らの右眼を抉った。血が弾け、男の空虚な右眼から血の涙が流れた。
「何をっ!?」
彼の声に男は静かに眼球を差し出した。
しかし、それで、てらてらと赤い血に濡れた眼球を受け取る者はいない。
「……これを、永遠の司王に――」
男は言い終わると同時に差し出された手が地に落ちた。
血に濡れた手のひらから、ころりと眼球が滑り落ちる。
その瞬間、男の体は霧散するように風に溶けて消えた。
彼が何かを言う暇すらなかった。
余りにもあっけない消滅に男は幻だったのかと思うくらいだった。
しかし、地面に転がる眼球が、男が確かに存在していたのだと主張していた。
彼がどうしたものかと躊躇っていると、周辺の精霊たちが眼球を持ち上げて、受け取るよう急かした。
「……」
小さな溜め息を吐いて、彼は仕方なく、それを受け取った。
そして、彼は自分が受け取ったものが眼球ではないことに気付く。
確かに眼球であったはずのそれは漆黒の宝玉と転じていた。
「まあ、いいか」
変化の理由より、持つ物が眼球ではないことの方が、余程、彼にとって重要だった。
誰だって、眼球より宝玉の方がいいに決まっているのだ。
そして、彼の脳裏に男の遺言としか思えない言葉が過ぎる。
関わり合いたくないが、遺言を無視するには後味が悪かった。
「永遠の、司王……」
彼は呟いて大きく肩を落とし、嘆息した。
折角、此処まで来たことが無駄に終わりそうな予感がした。
三
招待者である男と夕食を済ませ、彼は適当な理由を作って、部屋に戻ると、大きな溜め息を吐いた。
これから呼び出す相手のことを考えると、恐ろしく気が萎える。しかし、呼ぶしかない。
手の中にある漆黒の宝玉を『永遠の司王』とやらに渡すにはこの手段しかないのだから。
彼は『永遠の司王』などという人物は知らない。
だが、似た響きを持つ存在なら知っている。
慈悲という名を持ち、人ならぬ存在から『慈悲の司姫』と呼ばれる存在を、彼は不本意にも知っていた。
覚悟を決め、彼は口を開く。
「グナーデ」
彼が呼んだ名に、周囲にいた精霊たちが気を引かれて顔を上げる。
そして、嬉しそうな表情になった。
その瞬間、ふわりと何もない空間から漆黒の刺繍入りのベールを被った喪服の女が現れた。
そして、喪服の女は軽い靴音を立てて、降り立ち、彼を見ると、くすくす……と笑った。
「ご機嫌如何? なんて訊くまでもないわね」
その言葉が示す通り、彼は渋面だった。
誰が見ても機嫌が良いとは判断しないだろう。
「それで、何の用? 願い事でも決まって?」
彼は渋面のまま、漆黒の宝玉を差し出した。
それを見て、喪服の女はベールの内で顔色を変えたようだった。
「それは――」
「誰かは知らないが、『永遠の司王』に渡してくれと言い残して逝った」
彼の言葉に喪服の女は静かに頷いた。
「確かに、属性は私と異なるけれど、我が一族のものね」
「やっぱり知っているんだな? では、渡しておいてくれ」
確認を取るや否や彼は喪服の女に漆黒の宝玉を押し付けた。
そして、何か言われる前に口を開く。
「言っておくが、私は此処に休暇で来ている。巻き込まれる気は毛頭ない。ただ、一応、最期を看取った者として義務を果たしたに過ぎない」
さっさと帰れと言外に告げると、喪服の女は小さく笑った。
「構わないわ。現時点では貴方に頼みたいことはないもの」
それは、つまり、何か。必要さえあれば、巻き込むと言いたいのだろうか。
彼が憮然として睨み付けると、喪服の女は鈴を転がすような涼やかな笑い声を響かせた。
「安心なさいな。この宝玉の主は闇に属する私とは逆の光に属する者。『永遠の司王』も、そうよ。余程のことがない限り、私が関与することはないのだから」
「?」
眉をひそめる彼に喪服の女は詩でも吟ずるような調子で言った。
「光と闇は一対。相反し、相通ずるもの。世界の天秤の両の皿に乗るもの」
そして、喪服の女はくすりと笑う。
「もっとも、私一人が関わったところで傾くような危うい天秤ではないのだけれど」
そう呟き、喪服の女は彼に説明した。
「基本的に闇に属する私たちは単独行動を好み、光に属する彼らは団体行動を好むのよ。だから、必要以上に関わり合いにならないようになっているわ」
その言葉に彼は妙に納得した。
どう考えても、この喪服の女に協調性はない。団体行動など望めそうにない。
自分の好きなように動いて、それで誰かに迷惑がかかるなどと思いやるなどしそうになかった。
「これは私が預かり、届けておきましょう」
そう告げると、喪服の女は瞬く間に掻き消えた。
「……」
あっさりと去った喪服の女に、彼は拍子抜けした。
考えて気に病んでいたことが愚かなことだったように思えてくる。
「まあ、合理的な女だからな」
喪服の女は嫌になるくらい合理的で、人の感情を無視してくれるが、今回ばかりは良い方に働いてくれたようだと呟くと、彼は安堵の溜め息を吐いた。



| |