黄昏の契約Ⅲ
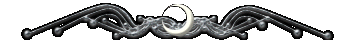
大切なものを護り続ける意志。
大切だから護り続けるのか。
護り続けるから大切なのか。
彼女は笑って答えた――「重要なのは望んだという事実」と。
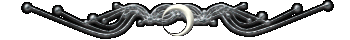
一
さわさわさわ……
さわさわさわ……
さわさわさわ……
さわさわさわ……
墨を落としたかのような闇の世界に風による葉擦れの音だけが響き渡る。
時は深夜。
すべての生命が眠りに就く時刻。
人ならざる者たちだけが気付いた異変。
ざあぁ――……
古い鐘撞き堂が文字通り消滅した。周囲に全く被害を与えることなく忽然と姿を消す。
さながら、最初から存在しなかったように。
ぽっかりと空虚な空間を生み出して。
くっきりと何もない地肌を晒させて。
さらさらさら……
さらさらさら……
さらさらさら……
さらさらさら……
厚い雲からわずかに覗いた弓月に照らされた世界に風に揺れる衣擦れの音が響き渡る。
空には一つの影。
誰も見上げることのない空の影。
人ならざる者たちだけが耳にした呟き。
「残るはひとつ……」
始まりは遥か昔。
終わりは遥か彼方。
しかし。
今、この時、時の歯車を止める楔は引き抜かれていく。
ニ
それは長閑な昼下がりの城での出来事だった。
近道となる奥庭を通り過ぎようとした彼は思わぬ人物の姿を見つけて驚愕した。
幼い少年が枯れた噴水の前で立っていた。
「……こんな所で何をしていらっしゃるのですか、殿下?」
驚かさないように声をかけると、この国の王の唯一の嫡子である少年はかすかに眉をひそめながら彼を見た。
そして、少年は彼の風体を見て取り、問い掛けた。
「その方は聖騎士団の者か?」
「はい」
彼の方は何かと行事の折で、少年の顔を知っているが、少年の方は彼のことは知らなくて当然である。
何しろ、彼は名ばかりの聖騎士団の一人で、目立った功績もない。
別に不満がある訳でなく、むしろ穏やかに暮らせたら良いと最近の経験で実感している彼だ。
本当は少年のことも見なかった振りをしたかったのだが、やはり、そうもいかず声を掛けた次第だった。
「ならば、手伝ってくれ。探し物をしているのだ」
幼い少年らしからぬ口調に彼はわずかな戸惑いを感じた。
しかし、王族の、しかも嫡子で世継ぎだ。そのような物言いを躾けられたのかと考え直して頷く。
「はい。何をお探しなのですか?」
少年は辺りを見回しながら答えた。
「真鍮の箱だ。この辺りに隠して置いたのだが、忘れてしまった」
「隠す?」
疑問が顔に出ていたのか、少年は小さく笑って答えた。
「私の宝物だ」
何処か大人びた仕草だったが、告げられた内容は子供らしいものであり、彼は納得する。
「箱、ですか。もしかして、お埋めになられたとか?」
少年に倣うように辺りを見回しながら彼が尋ねると、少年はすぐに否定した。
「いや。埋めてはいない」
その答えに彼は改めて周囲を見回した。
見落とさないようにゆっくりと丹念に視線をやると、不意に常緑樹の低木の枝の間に何か見えた。
「殿下」
呼びかけて彼は低木の側に寄り、軽く枝を掻き分けた。
後を追った少年は彼の後ろから覗き込むと、微笑みを浮かべた。
「ああ、これだ」
そう言って少年は大切そうに真鍮の箱を手に取った。
そして、箱の下に付着した土を丁寧に払い、彼を見上げた。
「感謝する。助かった」
心からの礼に、彼は面映く感じつつ、笑みを浮かべた。
「いいえ、お役に立てたようで何よりです」
そして、少年はもう一度礼を言うと、真鍮の箱をしっかりと抱きながら去っていった。
それを見送った彼は不意に思った。
言葉は少なくとも、あれだけ感謝の心を感じられるのだ。
なのに、言葉数は多いくせに全く感謝の心が伝わって来ないのは、やはり、相手が人外の存在だからなのだろうか。
そうして、思い浮かんだ喪服の女の姿に彼は小さな溜め息を吐いた。
三
思いがけない交流をした夜、自分の館の私室にいた彼は、最近すっかり慣れ親しんでしまった異形の精霊たちに誘われ、露台に出た瞬間、やはりと思ってしまった。
近頃、聖都では奇妙な出来事が起こっていた。
誰もが寝静まった深夜のうちに、一つの建物が丸ごと消失してしまう現象である。
朝になって気付いた近所の住民は最初、夢かと疑い、時間が経つに連れて混乱して、ようやく城に連絡する。
だが、連絡して捜査しても手掛かりとなるような形跡は全くなく、そうしているうちに六件の被害が出た。
幸いなことに消失した建物はすべて現在使用されておらず、人的被害はなかったのだが、ただ建国時代の建築物だっただけに歴史的価値があり、専門家たちの嘆きは深い。
数日前、彼は興味本位で消えた建物跡を見に行って、嫌な予感を抱くことになった。
最近、人外の存在を見る能力『聖眼』に目覚めた彼は建物が無くなった其処に、奇妙な紋様を見つけてしまった。
それが何を意味するのかは知らない。だが、彼の優れた『聖眼』は紋様に宿る尋常ではない力を彼に教えた。
それは明らかに人間業でなく、そして、この場合、彼は自分が巻き込まれてしまう可能性が非常に高いことを知っていた。
そして、彼の嫌な予感は見事的中した。
「こんばんは」
涼やかな声で挨拶をしたのは、露台近くの木の枝に腰掛けていた、刺繍入りの漆黒のベールを被った喪服の女だった。
以前に挨拶くらいしろと言ったことを覚えていたのか挨拶をした相手に彼は挨拶を返さねば何か言われると思った。
だが、口から零れたのは挨拶とは程遠いものだった。
「やっぱり来たのか……」
その言葉に喪服の女はくすくす……と笑って言った。
「まあ、酷い挨拶だこと」
笑いながらの言葉は詰るよりからかう響きが大きかった。
「やっぱり、と言うことは私が此処に来た理由を貴方は知っているのかしら?」
笑いを含んだ声音に何処か薄ら寒いものを彼は感じた。
この喪服の女の態度は鵜呑みに出来ない。
心の底から笑っていても、何処か冷静さを失わず、常に試されているような気がしてならないのだ。
だから、彼女と対する時、彼は常に気を引き締め、隙を見せないようにしていた。
「最近、起こっている建物の消失のことだろう」
その答えに喪服の女は困ったように小首を傾げた。
「間違ってはいないけれど、当たってもいないわね」
「何? 原因を調べに来たんじゃないのか? それで、私の力を使いたいのだろう?」
その瞬間、喪服の女は軽やかに笑い出した。
鈴を転がしたような美しい笑い声に惹かれ、精霊たちが彼女の許へと集まり、戯れる。
その幻想的な美しさと同時に感じる不吉さに彼は眉をひそめた。
「原因なんて調べる必要はないわ。それから、今回は貴方の『聖眼』の力を借りに来た訳でもないのよ」
「何だと?」
すう、と笑いを収め、喪服の女は静かに言った。
「私は確かめに来たの」
「……何を?」
警戒しながらの一言に、喪服の女がベールの内で一瞬だけ笑ったのを彼は感じた。
「最近、何かを『聖眼』で見つけなかった?」
「何か、とは何だ? 建物消失後の紋様……のことではないな」
「ええ、違うわ」
頭の回転が速い彼の言葉に、喪服の女は満足げに頷く。
「……そう、おそらく城で、本を」
「本?」
訝しげに繰り返した彼に喪服の女は少し考えて否定した。
「いいえ、違うわね。そのままであるはずがないもの。だから、本でなくてもいいの。城で何かを見つけなかった?」
城で見つけたと言われて思い浮かんだのは昼間の出来事だった。
だが、あれは喪服の女が関わるようなものではなかったはずだ。
第一、『聖眼』を使った覚えもないし、あの真鍮の箱には何の違和感も抱かなかった。
「いや、特には――」
「本当に?」
重ねて問われて、彼は仕方なく関係ないことだと断りを入れてから昼間の出来事を話した。
その瞬間、周囲の空気の色が変わった。
それまで、穏やかに流れていたものが張り詰めた緊張感に取って代わる。
「――グナーデ?」
思わず、喪服の女の名を呼ぶと、彼女は静かに言った。
「……王子は、貴方を聖騎士団の者かと確かめた上で、探させたのね? 王子が、貴方に――?」
「あ、あぁ」
彼が頷くと同時に喪服の女は密やかに笑った。
「そう、いうこと。では、尚更、早く事を成せねばならないわね」
小さく呟いたかと思うと、喪服の女は木の枝から浮かび上がり、消え去ろうとした。
「待てッ!!」
喪服の女が消え去る前に、彼がその腕を掴めたのは奇跡に等しかった。
彼は内心、自分の反射神経の良さを感心しながら、表情を険しくして問うた。
「何が起こっている!?」
「……その手を放しなさい。巻き込まれることは不本意なのでしょう?」
苛立ち半分、宥め半分の声音に、彼は更に表情を厳しくした。
「私が言ったことで、殿下の身に何か起こったら困る」
その言葉に喪服の女は微笑みを浮かべた。
ベールで隠されていても伝わる皮肉めいた空気に、彼は戸惑いを覚えた。
彼の戸惑いに気付いた様子もなく、喪服の女は言葉を矢継ぎ早に紡いだ。
「それは、どういう意味で言っているのかしら? 王家に従う者の義務感? 国民の自覚? 弱者への庇護欲? それとも、保身?」
喪服の女らしからぬ発言に彼は眉をひそめた。
言葉には紛れもない皮肉と焦り、そして、苛立ちが含まれていた。
それは別にいい。だが、告げる態度が解せない。
いつもなら、あの不快なまでに余裕を持った微笑みと共に言っているはずだった。
それは彼女に余裕がないということを示していた。
否、違う。余裕がない訳でない。
ただ、自分の言葉の何かが癪に障ったようだ。
珍しいと状況も忘れて思った彼だが、すぐに気を取り直して、相手の質問に答えた。
「強いて言うなら、殿下を気に入っている」
喪服の女の言っていたこと実は間違っていない。
だが、人ではない存在にとっては下らないと嗤いの対象でしかないようだし、何より彼女の性格を考えるとこの答えの方が気に入るだろうと思われた。
打算的かもしれないが、此処で彼女に置いておかれたら、間違いなく気を揉む羽目になる。
「……自分から関わろうという気なの?」
わずかな沈黙の後、喪服の女は静かに尋ねた。
すでに落ち着きを取り戻した様子だった。それも、表向きのことかもしれないが。
彼は顔を渋面にして、答えた。
「仕方ないだろう」
その瞬間、喪服の女は弾けるように笑い出す。
「……全く、これだから人間は愚かだわ。だけど、そうね。だからこそ、私は、私たちは愛しく思うのでしょう。今も昔も」
「何の話だ、それは」
言葉の内容が気に障り、彼が鋭く睨み付けると、喪服の女はくすくす……と笑って言った。
「いいえ、何も。ただ、私が気に病むことではなかったというだけのこと」
「は?」
眉をひそめて彼は胡乱げに喪服の女を見やった。
「気に病むって、まさかとは思うが、私を巻き込むことをとか?」
「あら、どうして私がそんなこと気に病まねばならないのかしら。貴方は巻き込まれたいのでしょう?」
「いや、それは」
違うと言いかける彼を制するように、喪服の女は言葉を続けた。
「これ以上、時間を無駄にしたくないわ。行きましょう」
そして、喪服の女は自分の腕を掴んでいる彼の腕を掴み返して、そのまま宙に浮かび上がり、夜の空を駆ける。
「おい、まだ、私は何も準備をっ」
突然の浮遊感に驚きながら、彼は叫んだ。
しかし、返って来た答えは実に冷淡なものだった。
「何の準備がいるというの? 私は貴方に何も求めていないわ。それに、今から会う相手は剣の一本や二本で、どうにかなる存在ではないのよ」
言外に役立たずだと言われたようなものだった。
文句の一つや二つ言いたい所だったが、状況が状況なので、彼は口を噤む。
代わりに彼は説明を求めた。
「それで、何が起こっているんだ?」
二度目の問いにも喪服の女は答えようとしなかった。
ただ、ちらりと彼を一瞥して、静かに告げた。
「私から説明する気はないわ。知りたいというから、連れて行くのよ」
実際に見聞して、自分の頭で考えろと言う喪服の女に、彼は改めて、いつか縁を切ることを誓った。



| |