黄昏の契約Ⅱ
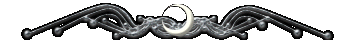
永遠に流転する命と魂。
永遠だから流転するのか。
流転するから永遠なのか。
彼女は笑って答えた――「それが生きている証だから」と。
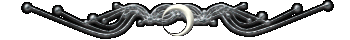
一
ごり、ごり、ごり、ごり、ごり……
彼女は一心に何かを細かく擂り潰していた。
「貴方、もう少し待ってね」
彼女は微笑みを浮かべて愛する夫に語りかけた。
「私の腕によりをかけて、美味しいものを作るから」
食卓には愛する夫が彼女の手料理を待っている。
最初の頃は慣れなくて失敗ばかりしていた。
けれど、今では手馴れて上手に作れるようになっている。
くつくつくつくつくつくつ……
「もう出汁も取れたみたい」
彼女は素早く出汁の素を鍋から取り上げた。
そして、食べ易く切った新鮮な野菜と肉を投げ込む。
しばらく煮込んで、最後の仕上げとばかりに擂りたての白い調味料を入れた。
そして、料理を皿に盛って食卓に並べた。
「さあ、召し上がれ」
彼女は自分も席に着いて小首を傾げた。
「どう? 美味しい?」
「ああ、とても美味しいよ」
「良かった」
愛する夫の言葉に彼女は嬉しそうに微笑んだ。
甘く幸せな時間が穏やかに流れていく――。
二
彼の平穏は唐突に終わった。
気持ちよく目覚めた朝は次の瞬間、不快に変わる。
彼は無表情に目の前の光景を見つめた。
驚嘆の声を上げず済んだ自分の胆力に彼は自分で感心した。
部屋を徘徊する異形の存在たち。
幸いにも醜悪な姿をしたものはいなかったが、最悪の目覚めだった。
彼は低く唸った。
「何だ、これは」
それは現実を自分に認めさせるための言葉だった。
事実、彼は自分が見ているものを知っていた。
約一ヶ月前、思い出すも腹立たしい喪服の女によって彼は知りたくもないことを教えられた。
自分が人外の存在を見る力『聖眼』を持っていることを。
その力を父の形見の勲章に宿る力で封印されていたことを。
周囲の異形の存在は精霊と呼ばれるものだということを。
だが、彼がそれらを見ていたのはたった数日の間だけ。
喪服の女に形見を奪われていた期間だけだった。
それを取り戻した後は元通りになったのだ。そう、少なくとも、昨夜までは。
封印のことを知ってから、彼は父の形見を前にも増して肌身離さず身に着けることを心がけていた。
彼は眉をひそめて呟いた。
「あの女が何かしたのか……」
彼にはそれ以外思い当たる節がなかった。
聖眼のことは誰にも話していない。
形見は自分の手元にある。
とりあえず、彼は寝台から降り、着替えを済ませ、朝食など一通りことを済ませた後、今後のことを考えた。
このままというのは冗談ではない。
癪に障るが、諸悪の根源と思わしき喪服の女を呼ぶしかないだろう。
明らかに人ではない喪服の女は約一ヶ月前に願いを叶えるという一方的な約束を押し付け、決まったら呼べと去っていった。
彼には呼ぶつもりはなかったし、こんな状況にならなければ一生呼ぶことはなかっただろう。
それぐらい彼は喪服の女に関わりたくなかった。
出来ることなら、最初からなかったことにしたいぐらいだ。
だが、過去は変えられない以上、仕方ない。
どうにか思考を前向きにし、彼は思案した。
幸いにも、今日は休暇の日である。
一瞬、今、此処で呼ぼうかと思ったが、すぐに彼は考え直した。
人払いをしても、屋敷には自分以外の人間もいる。
喪服の女の姿が見えても見えなくても変に思われる。
それは遠慮したかった。
そこまで考えて、彼は不意に不機嫌になった。
迷惑をかけられているのはこちらのはずなのに、どうして自分がここまで悩まなくてはならないのだろうか。
答えは簡単だった。
相手が人間でなく、こちらの都合など考えていないからだ。
実に不条理な現実である。
しかし、此処で考えていても現状が変わるはずもなく、彼は久しぶりに墓地に向かうことにした。
父親を尊敬していた彼は以前から頻繁に墓参りに行っていたが、其処で喪服の女に会うという災難に遭ってから、墓参りは控えていた。
屋敷の者たちに外出する旨を伝え、彼は墓地に向かった。
墓地は都の外れにあり、其処に行くには賑やかな街中を抜けなくてならなかった。
これから二度と会いたくない相手に会うのかと思うと憂鬱になった彼の足は自然と遅くなる。
だが、次の瞬間、彼は考え直そうと努力した。
これを最後にすればいいのだ。
願いも適当に些細なことを言って、縁を切ろう。
そうすれば、もう二度と悩まされることはなかろう。
そう思うとするのだが、彼の矜持が許そうとしない。
喪服の女の力を借りることに、どうしようもない苛立ちを感じていた。
考え事をしながら歩いていた彼は横の店から人が出てくることに気付かず、ぶつかった。
「きゃ!」
倒れる相手に咄嗟に手を伸ばして支えた瞬間、彼は表情を強張らせた。
彼がぶつかったのは喪服に身を包む女。
動揺しながら、彼は相手の顔を見やり、そして安堵の息を吐いた。
相手は彼が会おうとした喪服の女ではなかった。
栗色の髪に水色の瞳、柔和な顔立ち。
年頃も違う。
二十代前半に見える喪服の女より年上に見えた。
どうかしている。
いつだって誰かが死んでいるのだ。
喪服を着ているのはあの人外の存在だけではない。
「……大丈夫ですか? すみません、考え事をしていたので」
彼が謝ると、相手は淡い笑みを浮かべて言った。
「いいえ、私も余所見していたから」
そして、彼はふと気付いた。
相手の顔色が随分悪い。
余所見というより立ち眩みをしたのではないか。
「失礼ですが、随分と顔色が悪いですよ。少し休まれた方がいいのでは?」
「いえ、大丈夫です。家も近いことですし」
微笑みながら答える顔はやはり暗かった。
何か気にかかるものを覚え、彼は相手を凝視した。
それを心配されていると受け取ったのか、相手は心持ち顔を伏せた。
「本当に大丈夫なんです。ただ、先頃、主人が亡くなって、それで少し疲れているのだと」
彼は自分の父親が逝った時のことを思い出した。母は物心付く前に逝ったので、特に何の感慨もないが、父親は別だ。
やるべきことを終えた後、しばらく無気力なって食事を摂ることすら億劫になっていた。
この未亡人も似たような状況なのだろう。
彼は自然と申し出ていた。
「家が近いのでしたら、お送りしましょう」
未亡人は一瞬驚くが、躊躇いがちに頷いた。
未亡人の家は本当に近かった。
何度も礼を言う未亡人に恐縮しながら別れを告げ、彼は再び目的地である墓地に向かった。
三
丘の上にある広い墓地は人気が全くなかった。
彼は前に喪服の女が立っていた辺りまで来ると、不機嫌な声で呼んだ。
「グナーデ」
一瞬の静寂。
そして、変化が訪れる。
彼の前方の空間が揺らいだかと思うと、空中に喪服の女が現れた。
喪服の女は彼の姿を見て、地上に降り立った。
そして、刺繍の入ったベールで素顔を隠したまま小首を傾げた。
「願いが決まったの?」
挨拶も何もなしで本題を切り出す喪服の女に彼は渋面になった。
「お前たちには礼儀という言葉はないのか」
喪服の女は笑った。
「嫌だわ、あるに決まっているじゃない。でも、挨拶をしたところで貴方は挨拶を返してくれるの?」
彼は言葉を失った。
仮に喪服の女が挨拶しても自分は無視する。
それが礼儀に反することは明らかだった。
「一方的に要求されて応じる必要が何処にあるのかしら? 人間が自分勝手なことはよく知っているけれどね」
返す言葉がなかった。
いや、本当はあるはずだ。
だが、彼にはすぐには思いつかなかった。
「それで、願いは何かしら?」
前回と同様、あっさりと話を進めようとする喪服の女に苛立ちながら、彼は言った。
「私に何をした?」
「何のこと?」
「封印に何か小細工をしただろう!」
彼は今朝からのことを怒気が混じった声音で説明した。
すべてを聞き終えた喪服の女は静かに否定した。
「私は何もしていないわ」
反論しようとする彼を制して、喪服の女は続けた。
「言ったはずよ。私は約束を守る、と。けれど、貴方は人間ですものね。そう簡単に信じてはくれないわね?」
彼は無言で睨み付けた。
信じる信じない以前の問題だった。
喪服の女は小さな溜め息を吐いて言った。
「封印を見せて」
彼は勲章を見せた。
「封印の力は失われていない。以前と変わらないわ。だとすると、変わったのは貴方の方ね」
「何?」
彼が問うと同時に、喪服の女はベールを取って彼に近付き、少し宙に浮いて彼の双眸を覗き込んだ。
「っ!」
思わず、身を引こうとする彼の顔を両手で挟み込み、喪服の女は色違いの紫と翠の瞳で凝視する。
間近で直視した美貌に彼はぞくりとし、その背筋に冷や汗が伝った。
緊張の余り、息が止まる。
視線を逸らしたくても、顔は固定されており、何より逸らすことを相手の眼差しが許さなかった。くちづけするのかと傍目から見えるほど近付きながら、そこには一片の甘やかさはなく、彼は死に直面して気分で固まる。だが、漂ってきた芳しい花の香りに、前に頬に受けた唇の感触を思い出し、彼は訳もなく動揺した。そして、そんな彼に追い討ちをかけるように喪服の女が不意に微笑みを浮かべた。
「あら、まあ……」
純粋な驚きが籠もった呟きに彼は我に返り、喪服の女を振り払った。
喪服の女はすぐに離れて楽しそうな笑い声を上げた。
「何がおかしい!」
激昂して叫ぶ彼に喪服の女はベールを被り直しながら答えた。
「ああ、ごめんなさい。余りにも予想外だったから、思わず笑ってしまったわ。そうよねえ、聖眼の力を望まない貴方にとっては少しも楽しくないわよね」
謝っているが、その声には笑いが混じっていた。
彼は鋭く睨み付け、続きを待った。
「貴方の聖眼の力が強くなっているのよ。それが封印の力を超えてしまった」
「それは、お前が一度私から封印を奪ったせいか?」
だとしたら、やはり責任は喪服の女にある。
「いいえ、それは違うわ。貴方の聖眼の力は今も成長を続けている。私が貴方から封印を奪わなくても、今日には封印は役に立たなくなったわ」
くすりと喪服の女は笑った。
「これはすでに約束されたことだったのね。運命だと思って諦めたら?」
「出来るか!」
そう叫び、彼は腹立たしげに言った。
「……願いを叶えると言ったな? 今一度、封印しろ」
不本意だったが、それしかない。
願いも叶えさせて、これで終わりだ。
しかし、喪服の女の返答は無残だった。
「出来ないわ。それは無理よ。すでに在るものを否定するような真似は出来ないの。ましてや、聖眼の力は私たちとは違う性質の力。与えることも出来なければ奪うことも出来ない。貴方の望む封印は一生涯のものでしょう? それは否定と同じ、奪うのと同じ」
彼は頬を歪めて皮肉を言った。
「願いを叶えるというのは嘘だったのか?」
「いいえ? 私は願いを叶えると約束したわ。けれど、何でもと言った覚えはないわよ。私たちは万能ではないの。私たちもまた、世界に生きるひとつの生命に過ぎないのだから」
揺るがない声音に彼は舌打ちした。



| |