黄昏の契約
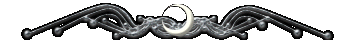
毒のある美しい花。
毒があるから、美しいのか。
美しいから、毒があるのか。
彼女は笑って答えた――「ただ、花は咲くだけ」と。
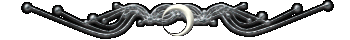
一
ぴちゃり……
ぴちゃり……
ぴちゃり……
ぴちゃり……
闇に響く、滴る水音。
投げ出された足から伝わり落ちる雫。
その雫を唇で掬い取り、それは恍惚の呻きを零した。
そして、細い手首を握り、力任せに引き千切る。
ごきっ……ぶちゅっ……
それは切断面から溢れる美酒で喉を潤し、その柔らかな肉を頬張った。
ごり……
固い骨が歯に辺り、それはうっすらと笑った。
そして、口の中から唾液で濡れたそれを取り出し、楽しそうに見つめる。
闇に浮かび上がる、白い骨。
しかし、すぐに興味を失ったのか、それは手にした骨を投げ捨て立ち上がった。
厚い雲に隠されていた月が姿を現す。
天窓から注がれる光に闇が照らされた。
それの側には片腕を失った女が一人。
生気を失った虚ろな双眸にそれの顔が映る。
それは赤い唇を歪め、笑った。そして、細い指先を伸ばした。
ぐちゅっ……
女の眼球を引き摺り出したそれは綺麗な宝石を見るように月光に翳した。
てらてらと輝く様は真珠のよう。
貝が自らの内に入った異物から生み出した真珠を人が無理やり取り出し、愛でるように、それは女の眼球を愛でた。
ぴちゃ……
赤い唇から伸ばされた舌が指先で摘んだ眼球を舐める。
その甘美な味にそれは身悶え、双眸を細めた。
そして、耐え切れず、眼球を口に含み、しばらく甘い飴を食べるように口内で転がし、飲み込んだ。
ほう……
それは感嘆の溜め息を吐き、再び女を見た。そして、薄く微笑み、手を伸ばす。
闇の中の晩餐はそれからしばらく続いた――。
二
「これで何人目だ?」
眉をひそめて呟いた言葉を耳聡く聞いた同僚が苦虫を噛み潰したような表情で答えた。
「十二人。今月に入ってからは五人目だ」
二人の視線の先には白い布で覆われた無残な遺体。いや、それを遺体と言っていいのだろうか。正確には、食い残しと言うべきだろう。
「周期が早くなって来ているな」
「ああ。これは本気で魔物の仕業かな?」
同僚の言葉に彼は薄く笑った。
「魔物? この聖都に?」
神を始祖に持つという王によって治められている国の首都。
聖都の名に相応しく、古い神殿が幾つも存在し、邪悪なる存在は近付けぬと謳われる永遠の都。
彼は皮肉げに続けた。
「そんな噂が立てば、聖都の名折れだろうに」
「だから上のお偉方は俺たちまで使う気になったのさ」
同僚の言葉に彼は鼻で笑った。
「聖騎士の血を継ぐという私たち聖騎士団が魔物を退治する、か? 如何にも大衆向けな話だな」
特殊の力を以って邪悪なる存在を討ち滅ぼしたと伝え聞く聖騎士。
その末裔によって構成された騎士団が聖騎士団である。
かといって、特殊な力はすでに失われており、聖騎士といっても普通の人間と変わりない。
同僚も同じように笑い、そして表情を改めて言った。
「実のところ、お前はどう考えている?」
彼はちらりと運ばれていく遺体を見て答えた。
「大方、何処かの阿呆が飼っていた肉食獣が逃げたのではないか? 人が食うにしても、それだと随分な大食漢だ」
「でなければ、魔物か? さしずめ、『人食い』だな」
彼は短い感想を言った。
「そのままだな」
三
「やあ。どうだね、調子は?」
城の上司に報告した帰り、彼は一人の男に声をかけられた。
亡き父の友人であり、近く義理の父になる予定の男だった。
彼は申し訳程度に会釈をして答えた。
「体の方は申し分なく。仕事の方は行き詰まっていますよ」
男は訳知り顔で頷いた。
「そうか、やはりな。本来、君のような人間が関わる事件ではないからな」
「ええ、どうもそのようです」
「だが、あの事件のせいで娘も怯えている。近く、顔を見せに来てやってくれ。聖騎士の末裔である君が側にいてくれれば、娘も私も安心する」
彼は微笑みを浮かべた。
始祖の王の時代から続く聖騎士の末裔とは今や名ばかり。
その血統だけに価値が置かれている。
権力はあるが、名誉はない男は自分の娘と彼を婚約させることで名実ともを手に入れようとしていた。
それを彼が知っていることを目の前の男は知らない。
「いずれ折を見て伺います」
「別に今日でも構わないが?」
彼は静かに首を横に振った。
「いえ。今日は父の墓参りの日ですので」
「そうか、そうだったな。ああ、では引き止めて悪いことをした。早く行くといい。急がなければ、帰る頃には日も暮れよう」
そして、彼は男に別れを告げ、墓地に向かった。
年季の入った古い墓地は都の外れの丘にあった。
彼の父が眠る墓は新しいため、奥の方にあり、其処に行くまで、かなりの距離を歩かなければならなかった。
墓参りを終え、帰る頃には男が危ぶんだように日も暮れ始めていた。
事件以来、夜は恐ろしい闇の領域だった。
急ぎ歩いていた彼は墓地に立つ喪服の女を見つけて足を止めた。
急がなければ日も暮れるというのに喪服の女は動く気配もなく、遠くに見える都を眺めていた。
訝しく思い、彼は喪服の女に声をかけた。
「こんな時間まで墓参りか? 急がなければ自分も墓の下で眠ることになるぞ」
喪服の女は驚いたように振り返った。
「――貴方、私が見えるの?」
刺繍の入ったベールと逆光で顔は見えなかったが、細い声は若い女のものだった。
彼は眉をひそめて喪服の女を見た。
事件の被害者は皆若い女だ。それを知らない者は誰もいない。
次の被害者になることを恐れ、女たちは日が暮れる前から家に閉じこもっている。
喪服の女は自分が見えるのかと言った。
それは逆に言うと見えるはずがないということ。
その瞬間、彼は喪服の女に斬りかかっていた。
「!」
喪服の女は彼の行動に驚きながらも、ひらりと躱した。
「何て乱暴なこと……。私が何をしたと言うのかしら?」
問いかける声は落ち着き払っていた。
彼は剣の柄を持ち直し、構えながら答えた。
「今の都に夜を恐れぬ者はいない。少なくとも、人間の中には」
その返答を聞き、喪服の女は笑った。
「ああ、だから夜を恐れない私は人間ではないと言うのね?」
喪服の女は否定しなかった。それどころか笑って肯定した。
「確かに私は人間ではないし、どちらかというと闇に属する存在よ。けれど、やはり突然斬り付けられる覚えはないわ」
「そうか。だが、杞憂は早くに取り除きたいのだ」
彼は喪服の女が『人食い』であろうとなかろうと剣を退く気はなかった。
喪服の女はくすりと笑った。
「心配性なのね」
余裕の態度の相手を彼は鋭く睨み付けた。
喪服の女は不意に息を呑む。
「まあ! 貴方、聖眼を持っているのね? 道理で私のことが見えたはず。でも、封印されている。不思議だわ。それで、どうして私が見えるのかしら?」
首を傾げながら訳の分からないことを呟く喪服の女に彼は再び斬りかかった。
鋭い斬撃を驚くような俊敏さで躱し、喪服の女は彼の横を擦り抜けた。
「!」
その瞬間、彼は懐にあった父の形見である勲章が奪われたことを知った。
「貴様!」
振り返り様、放った一撃を喪服の女は踊るように避けた。
そして、軽やかに笑いながら言った。
「これはしばらく私が預かっておくわね。きっと明日には素晴らしいものが見えるわよ」
言い放つと同時に、喪服の女は姿を消した。
どんなに彼が見回しても喪服の女の姿を見つけることはできなかった。
代わりに日が完全に落ちようとしていることに気付き、彼は仕方なく今日は諦めることにした。
四
翌日、彼は朝から不機嫌だった。
喪服の女が言った「素晴らしいもの」とはこれのことだろうか。
だとしたら、趣味が悪いにも程がある。
視界の隅に映った醜悪な子鬼の姿に彼は顔をしかめた。
朝から彼が見たもの――それは浮遊する人面の炎であり、奇怪な虫であり、影に居座る醜悪な化け物だった。
これでは聖都ではなく魔都と言った方が正しいだろう。
しかも、気味の悪いそれらは彼以外の誰にも見えていなかった。
彼は一通りの仕事が終わると同時に昨日も行った墓地に向かった。
何をしたのかは知らないが、喪服の女が原因であることは察しが付いていた。
昨日、喪服の女が立っていた場所まで来たが、その姿は何処にも見当たらない。
彼は思わず舌打ちした。
その時、何かが視界を過ぎる。
例によって「素晴らしいもの」かと思ったが、それは蝶の翅を持った手のひら程度の大きさの少女だった。
それまで見たものとの違いに驚き、彼は無意識に掴んだ。
「きゃああん。何するのよぉ!?」
少女の悲鳴を無視して、彼は呟いた。
「何だ、これは?」
答えは思わぬ方向から返って来た。
「精霊よ」
聞き覚えのある細い声に彼は驚いて振り向いた。
喪服の女が立っていた。
「何だと?」
「物分かりが悪いわねぇ。精霊だと私は言ったの」
「精霊? これが?」
「いい加減離さないと、痛い目に合うわよ? 痛いのが好きだというのなら別にいいけれど」
精霊だと言われた少女はそれまで可憐さを失い、醜悪な姿に変わりつつあった。
身の危険を感じ、彼が手を開くと、少女は逃げるようにも服の女の許に飛び去った。
くすんと可憐な姿で泣く少女を喪服の女は慰めるように優しく頭を撫でて言った。
「危ないところだったわね。折角、可愛い姿になれたのに元に戻るところだったわ」
少女は泣き止むと喪服の女に笑いかけて消えた。
「どういうことだ、これは?」
訳の分からない状態に彼は苛立っていた。自然と声に怒気が混じる。
しかし、喪服の女は動じた様子もなく、笑った。
「言ったでしょう。貴方は聖眼の持ち主だと。聖眼――人外の存在を見る力のことよ。貴方たち人間は光に属する存在を敬い、闇に属する存在を厭うけれど、それらは本来同じ存在なのよ。ただ、方向性が違うだけ。力の弱い精霊はその土地の気に影響され易いから、聖域と言われる土地では美しく清いものに、穢れた土地では醜く邪なものに変わる。貴方が今日見た醜い存在もまた精霊よ」
その説明に彼は皮肉めいた微笑みを浮かべた。
「だとすると、聖都は穢れた土地ということか」
喪服の女は少し首を傾げて否定した。
「そうではないわ。ただ、今、この都は歪んだモノが存在するから」
「歪んだモノ?」
「そう。歪んだモノ」
喪服の女の声が真剣なものを宿す。
「私はそれを追って来たのよ。私の責任において処理するために。そして、それは貴方も探しているのではない?」
「……『人食い』か」
喪服の女はくすりと笑って言った。
「貴方たちは、そう呼んでいるの? あれも元は人間だったのよ」
「何?」
喪服の女は歌うように告げた。
「ずっと昔のことよ。一人の女が男に捨てられて自害したの。哀れな娘、愛しい娘。心の闇に囚われ、愛した男を憎むのを恐れて自らの命を絶った愚かな娘。余りにも愚かだから、死ぬ間際に囁いたの――願いを一つだけ叶えてあげる、と」
喪服の女は踊るように歩き出した。
彼はその後を追った。
「彼女は願ったわ。もう一度だけ愛する人に会いたいと。何てささやかな願い、慎ましい願い。その者に裏切られて死ぬというのに愚かな願い。それでも、私は叶えてあげたの。死せる躯に力を注ぎ、束の間の生を与えた。娘は男に会いに行って……そして、戻って来なかった」
「何故?」
喪服の女は一度足を止めて肩越しに彼を振り返った。そして、軽く肩を竦めた。
「彼女の心は彼女だけのもの。私が知るはずないでしょう?」
再び、喪服の女は歩き出す。
「けれど、事実だけは知っているわ。娘は男を殺したの。そして、一緒にいた新しい女を食べたのよ。そして、姿を変えて……今はあそこにいるみたいだわ」
そう言って喪服の女が指し示したのは城だった。
「……城に、その娘が?」
「もう人間でもないわ。ただの歪んだモノ。私が与えた力の気配を追って、此処まで辿り着いたけれど、それが限界。余りにも歪み過ぎて分からない。だから」
「だから、私の聖眼の力を借りようというのか」
喪服の女はベールの内で微笑んだようだった。
「貸してくれたら、これを返してあげる」
喪服の女が取り出したものを見て、彼は唸った。
「それは元より私のものだ」
「あら、違うでしょう? 貴方に聖眼を封じる力なんてないもの。これに宿った封印の力は違う人のものよ」
「私の父のものだ」
喪服の女は納得したように頷いた。
「そうなの。余計なものを見て苦しまないようにという親心なのね」
そして、喪服の女は笑った。
「だったら、尚更返して欲しいでしょう?」
「貴様……」
殺意すら込めて彼は睨んだ。
「その代わり、貴方の願いを一つだけ叶えてあげるわ。安心して? 私は約束を守るわよ。いつだって裏切るのは人間の方だけど、だからといって私まで裏切るなんて浅ましい真似はしたくないもの」
彼には承諾する途しか残されていなかった。



| |